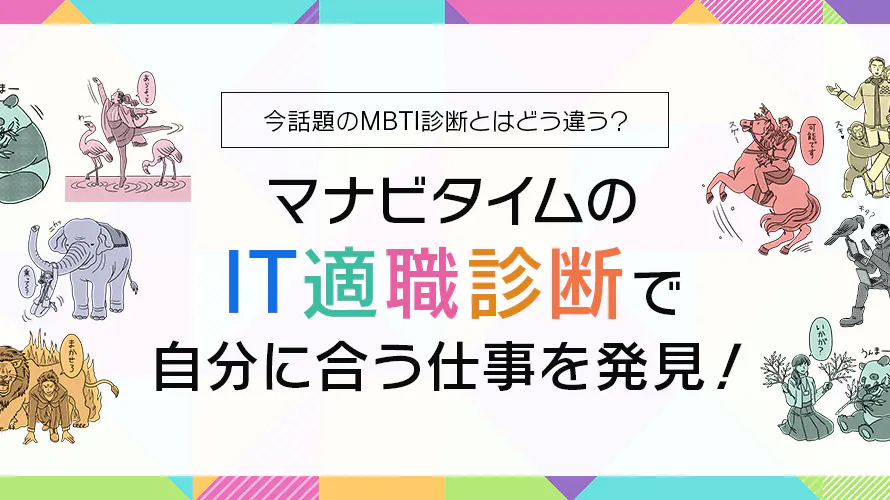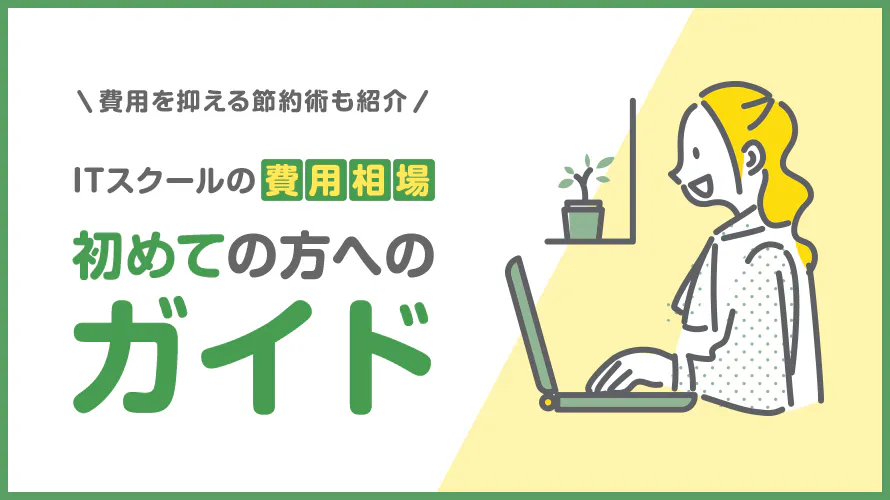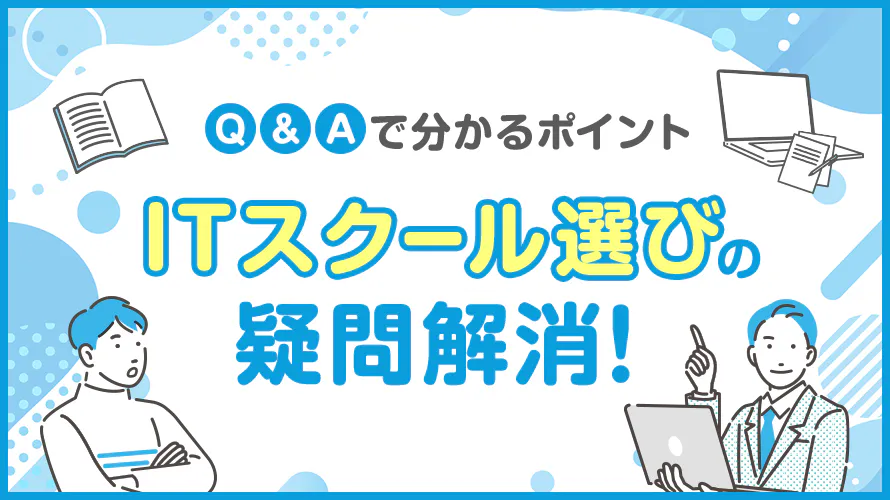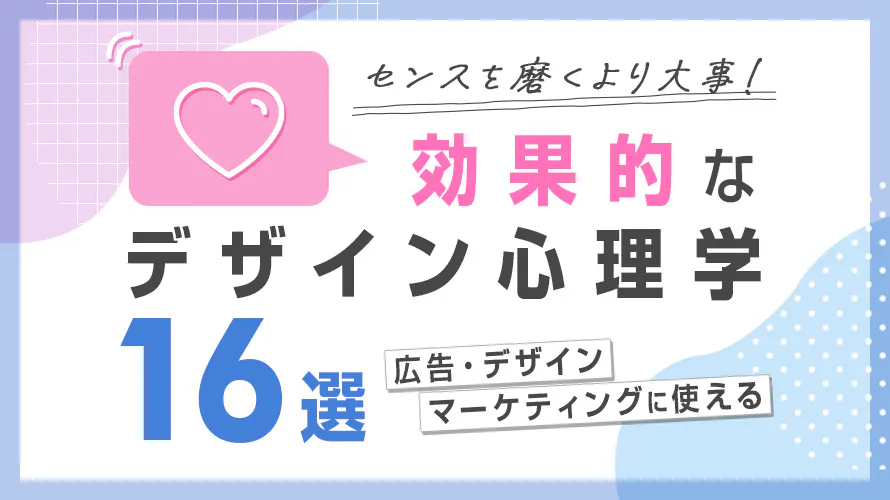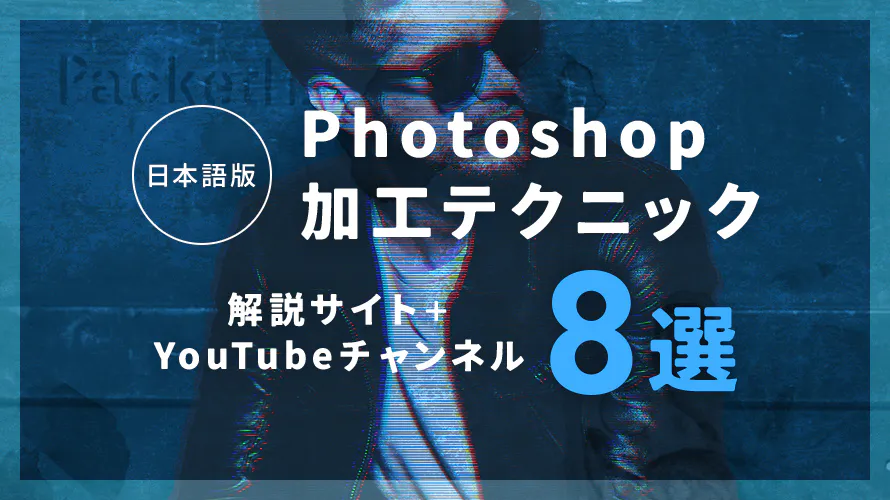Webサイト コンセプトメイキングの手法とフロー
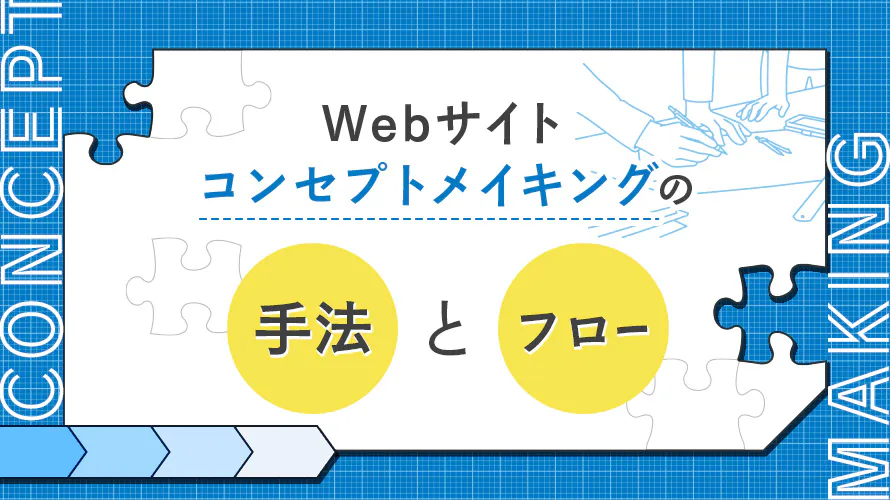
Webサイトの制作やリニューアルを企画する際、最初に行うことがコンセプトメイキングです。
コンセプトメイキングとは、そのWebサイトが持つ価値や目的を定義することです。最初のコンセプトメイキングがずれていれば、望んだ成果を得ることはできないでしょう。
例えば、問い合わせ獲得が目的のWebサイト企画なのに、チーム全員にそのコンセプトが伝わっておらず、ブランディング重視のデザインに仕上がってしまうといった可能性があります。
今回は、Webサイトの制作やリニューアルに欠かせないコンセプトメイキングについて、プロセスや必要な分析手法などを解説し、具体的なコンセプト設計方法を紹介します。
コンセプトメイキングの重要性
すべてのWebサイトは、何らかの目的の元に存在しています。それぞれのWebサイトがユニークなテーマを持っており、アクセスしてきたユーザーに伝えるべき情報や取ってほしい行動が用意されています。
また、場合によってはユーザーとコミュニケーションを取ったり、特定の機能・サービスを提供するために存在するものもあります。
Webサイトが持つデザインやナビゲーション、システムなどの要素は、こうした目的を達成するために存在しているのです。そして、求められる機能によって、必要なサーバースペック、開発言語、開発コストや期間、データベース仕様などが決まっていきます。
Webサイトのテーマやコンテンツ、想定するユーザー層、デザインの方向性、必要な機能など、Webサイトを構築する根幹となる部分を決める指針のことをコンセプトと呼びます。
コンセプトメイキングとは、Webサイトの目的を明確化し、それを実現するたけのデザインやサービスの全体像を決定していくステップのことです。
コンセプトメイキングがあいまいなまま制作を進行すると、制作途中の変更が多発しスケジュールが遅れたり、予算が増加したり、まったく目的に叶わないものができてしまうことや、そもそもプロジェクトが挫折してしまうこともあります。
コンセプトメイキングは、新規のWebサイト制作時はもちろん、大規模なリニューアルの際、継続的な運用においても必要不可欠です。
コンセプトメイキングのプロセス
コンセプトメイキングは、アクセス解析やリサーチ調査による分析的なアプローチと、意思決定者へのヒアリングや商品・サービスの情報などを元にした目的からのアプローチがあります。分析的なアプローチでは、課題点や問題点を発見します。そして、ヒアリングや商品・サービスの仕様や想定できるターゲット層などから、目的を具体化します。
それがWebサイトの目指す方向性となり、さらに実現性や具体的な目標数値などを加え、コンセプトと定義するのが一般的です。
決まったコンセプトは、関係者全員で共有する必要があります。それにより、制作途中で意見やアイデアが出たとき、「それはコンセプトに叶っているから実施しよう!」「コンセプトから外れているから別の方法を考えよう」などと、プロジェクトをスムーズに進行できます。
分析的アプローチの手法

Webサイトの目的や種類、業界によって必要な分析手法は様々です。
Webサイトのリニューアルでは、自社のアクセス解析が中心になり、課題や問題点を抽出するのが一般的ですが、合わせてベンチマーク(競合のWebサイト)も調査することで、より課題が明確になったり、差別化のためのアイデアを得たりすることができます。
新規Webサイトの制作であれば、自社データがないため、競合調査やアンケート調査など、また別の視点から分析する必要があります。
いずれにしても、一つの手法だけで完璧な分析を行うことはできないため、複数の分析手法を取り入れ、多角的な分析を意識しましょう。
ここからは、一般的に使われる分析手法について紹介します。
分析的アプローチ① 環境分析
ビジネスを左右する要因には、大きく外的要因と内的要因があります。
外的要因とは、自社がコントロールできる範囲外による影響です。「テロによる社会不安により海外旅行サイトの売上が落ち込んでいる」や「為替レートの変動により海外の安価な商品が広がってきている」などがあります。よりWebサイトに直結する例としては、「Googleのアルゴリズム変動により自社サイトの検索順位が低下した」などがあります。
内的要因とは、自社がコントロールできる範囲内で発生する要因で、「商品の在庫管理がうまくいかず購入機会を失ってしまった」「契約したサーバースペックが低く、Webサイトが重い」などです。
こうした内的要因と外的要因を合わせて分析し、課題や問題を発見する手法が「環境分析」です。
環境分析はマクロ(大きな)視点が必要になるため、場合によっては外部の調査会社、コンサル会社を活用したほうがいいかもしれません。
分析的アプローチ② ユーザー視点の分析
コンセプトメイキングがうまくいかない例として、最もよくあるのは「ユーザーの視点を考慮していない」ことです。
コンセプトメイキングを行うWeb担当者や意思決定者、チームメンバーは内部の人間なので、自社の商品・サービスが素晴らしく、使い慣れたWebサイトと感じているかもしれません。しかし、重要なことは初めてその商品・サービスを認知した、初めてそのWebサイトに訪問したユーザーにとって魅力的かどうかです。
また、商品・サービスのターゲット層が20代女性なのに、コンセプトメイキングに関わる意思決定者が50代男性である場合などは、ユーザー視点の分析を徹底しないと、最終的に目的が達成できないWebサイトになる可能性があります。
ユーザー分析では、知りすぎているからこそ見逃してしまう課題や問題点を見つけます。分析には既存顧客やターゲット層へのアンケート調査やインタビュー調査、ユーザーテスト(ユーザーにWebサイト上で特定の目的のために操作してもらいその過程で気づきを得る手法)などが有効です。
自社スタッフで分析すると商品・サービスを知りすぎているために抜けや偏見が生まれます。LINEリサーチのように、手軽に始められるリサーチサービスも多く登場しているため、外部のサービスを利用したほうがいいでしょう。
分析的アプローチ③ シナリオ分析
実際にターゲットユーザーがWebサイトを利用する際、どのような経路で訪問し、どういった情報(ページ)を閲覧し、どのようにタスクを実行してサービスを利用するのかを調べる手法をシナリオ分析といいます。
すでに固定客が多いショッピングサイトであれば、以下のようなシナリオが想定できます。
多くのユーザーがブックマークから訪問するでしょう。その後、目的のカテゴリページへ遷移したり、検索ボックスから商品を検索したりします。表示された商品一覧から商品の概要を把握し、気になったものの詳細ページに移動します。その後、購入を決めればカートに入れ、後で考える場合はお気に入りリスト等に入れるでしょう。いざ購入する際は、マイページにログインし、決算手続きを取ります。
このように、ユーザーが実際に取るであろうシナリオを想像したり、アクセス解析などで導き出したりすることで、無駄なページはないか、目的までに不要なページ遷移がないか、必要な情報を必要なタイミングでアプローチできているかなどを知ることができます。
現行サイト分析
リニューアルの場合、現行サイトの分析は最も基本的な分析事項です。
現行サイト分析には、使いやすさを分析するユーザビリティ解析、アクセスログを元に分析するアクセス解析、顧客の行動に焦点を絞って分析するミクロ分析、ユーザーがブラウザ上で行う行動を分析する行動フロー分析やヒートマップ分析などがあります。
最も一般的なツールはGoogleアナリティクスですが、基本的にはアクセスログを元にしたアクセス解析というマクロ視点の解析しかできません。
Googleアナリティクスも必ず確認すべきですが、必要に応じてユーザーテストやヒートマップツールの導入等を検討しましょう。
競合サイト分析
競合サイトの分析は、自社サイトの分析と同じかそれ以上に重要です。ユーザーは比較検討段階において、自社サイトと複数の競合サイトを比較し、最もいいと思った商品・サービスを利用します。
そのため、競合分析を通じて競合と比較し勝っている点は何か、劣っている点は何かを発見します。コンセプトメイキングでは、勝っている部分を伸ばし、劣っている部分を改善する方法を考えます。
競合分析では、SimilarWebやAhrefsといった競合調査ツールを用いたり、実際に競合サイトを使い、課題や問題を発見していくのが一般的です。
トレンド分析
社会動向やマーケット動向などのマーケティングトレンドから見た分析を、トレンド分析といいます。
Webサイトでは、新しいデザインや考えが次々登場するため、求められるデザインや機能のトレンドも日々変化しています。以前はFLASHや動画を用いたリッチコンテンツが主流でしたが、最近のトレンドとして重視されているのは「表示スピード」です。
そのため、デザイン要素を省いて表示速度に特化したデザイン手法が多く登場しています。また、Webだけでなく、商品・サービスの流行も重要なトレンド分析の対象です。
マーケティング分析
Webサイトの目的は様々ですが、いずれにしてもマーケティング的なアプローチが必要です。
例えば、Googleしごと検索(Google for jobs)という、Googleの求人検索が2019年1月23日に導入されました。オフィシャルサイトであれば、求人募集が目的の一つにあるかもしれません。その場合、Googleしごと検索に取り上げられるには、それに適したコーディング、マークアップが必要です。
また、ECサイト等であれば、プロモーションの候補にダイナミックリターゲティングがあります。ダイナミックリターゲティングを利用する際も、最初から必要なタグや商品データフィードを意識して制作するとスムーズになります。
さらに、リードジェネレーションやリードナーチャリングを行い、収益性を最適化させる場合、MAツールなどのマーケティングプラットフォームを導入する必要があるかもしれません。
コンセプトメイキングのタイミングでこうしたマーケティング的なアプローチを行えば、目的を達成するための手法を取り入れやすくなります。
目的的アプローチの手法

コンセプトメイキングでは、分析的アプローチとともに目的的アプローチ(関係者へのヒアリングや商品仕様の把握)などを通じて、提供するサービスや目的を具体化していきます。 具体的には、下記のような内容を意思決定者やチームメンバーにヒアリングするといいでしょう。
- なぜそのWebサイトを作るのか?
- Webサイトのターゲットはだれか?
- ターゲットに何を提供したいのか?
- ターゲットにどんな印象を持ってもらいたいか?
- Webサイトからサービスを提供するメリットは何か?
- メリットは誰が、いつ、どこで、どのように受けるのか?
- そのWebサイトは今のサイトと何が違うのか?
- そのWebサイトをいつ実現したいのか?
- そのWebサイトをどのように実現したいのか?
- そのWebサイトにかけられる予算はどのくらいか?
実際にはもっと深く聞きこんでいく必要があるかもしれません。また、こうした質問だけでなく、そもそもの商品の仕様や購買フローなども、Webサイトを作る前に理解しておく必要があります。
コンセプトの設定
こうしたアプローチを重ねることで、様々な課題や問題、強みや提供したいもの、目的が見えてくると思います。こうした情報を元にしてコンセプトを設定していきます。
調査やヒアリングを行う中で、様々な情報が得られ、伝えたいことが大量に出てくると思います。しかし、コンセプトは関係者全員が共有し、Webサイトの制作と運営の軸となるものなので、ポイントを絞りシンプルにしたほうがいいでしょう。
具体的には、次の要素のどれかまたは2,3個を強調したコンセプトになることが多いでしょう。
ターゲット
サービスの対象となるターゲット層を年齢や性別、居住地や立場などの属性によって具体化したものをコンセプトに組み込みます。ターゲットは、Webサイトの制作や運営に大きな影響を与えます。
例えば、ターゲットが女性なのか男性なのかで、テーマカラーやキービジュアルなど、デザインの方向性が大きく変わります。他にも、観光客がターゲットであるリゾートホテルでは、ホテル回りや部屋、温泉施設、料理などの写真が中心です。
一方、同じホテルでも、ビジネスユーザーが多いビジネスホテルでは、宿泊料やアクセス、ネット環境などが前面に出るなど、ターゲット層によってコンテンツのあり方も大きく変わります。
また、Webサイトの制作だけでなく、運用、マーケティングでも、ターゲット層は非常に重要です。ビジネスパーソン向けのプライベートなサービスであれば、平日の昼間ではなく帰宅時間や帰宅後の時間を狙ってプロモーションすべきでしょう。
ターゲットは、デザイン、機能、コンテンツ、プロモーションのすべてに関わる重要な要素です。
ポジショニング
競合サービスや市場の中で、提供するサービスの位置付けをポジショニングといいます。
他のWebサイトと何が違い、どんなカテゴリのサービスを提供しているのかなど、競合や市場との比較や関係性により、適切な位置(ポジション)を取る必要があります。
例えば、世界最大のECサイト「Amazon」は、「地球最大の書店」というポジショニングでスタートしました。まだ規模が小さかった時から、利用者の中で「本を探すならとりあえずAmazonを見よう」というポジションを得たため、他のECサイトがまねできない圧倒的な成長を果たしました。
オリジナリティ
ポジショニングは競合と比較したうえでの位置づけですが、オリジナリティは、他のWebサイトにない独自性を打ち出すことを指します。
例えば、MONOCOというECサイトは、他にはない一点ものは限定ものばかりを集めたサイトです。商品数ならAmazonや楽天には到底及びませんが、「ここでしか買えないものがある」というオリジナリティから多くの利用者がいます。
画像:MONOCO
これは情報を提供するメディアサイトの場合、特に重要です。他のメディアも取り扱っている内容と同じ情報を提供しても、利用者が増えることはないでしょう。ビジネス向けニュースアプリのNEWSPICKでは、他のメディア記事もありますが、「NEWSPICKオリジナル」という他にはない独自の情報を提供することで、ニュースアプリとしての地位を築いています。
Webサイトの達成目標
そのWebサイトを作成する目的を盛り込むことも重要です。これは具体的な数値で明示しましょう。
例えば、「月間PV数10万を達成する」という目標をコンセプトに組み込んだとしましょう。実際にWebサイトの制作や運用の中で、月間10万PVを達成するにはどうすればいいでしょうか。主要キーワードの検索ボリュームが月間1万なら、SEO対策を行っても目的を達成できないことになります。では、Twitterなど拡散力のあるSNSを用いるべきか、広告手法を取り入れるべきかといった議論になります。
例えば、「月間問い合わせ数100件」という目標をコンセプトに組み込んだとしましょう。仮にコンバージョン率が1%であった場合、必要なアクセス数は1万です。制作や運用の段階では、1万アクセスを集める方法、コンバージョン率1%を達成する方法などが議論になります。
このように、具体的目標があることで、Webサイトの制作や運用において、質の高い議論を行うことができます。
中長期的ロードマップ
ロードマップとは、Webサイトの制作と運営における中~長期的な計画を指します。Webサイトは公開して終わりではなく、運営し続ける必要があります。また、目的によってはフェーズを分け、それぞれのフェーズに適切な施策を行うことで最終目標に近づけていく必要があるでしょう。
例えば、メディアサイトであれば、公開後しばらくはコンテンツを追加し、とにかくアクセス数を増やすことが課題になります。この段階では、コンテンツを作ることはもちろん、プレスリリースや広告等も有効な手段でしょう。次の段階では、きちんと成果を得ることが課題になります。ここでは、フォームへの導線強化やコンテンツオファーなどが重要な施策になってきます。
また、大規模なサイトであれば、まずは中核となるサービスから公開し、順次関連サービスや必要機能を追加する方法をとる必要があるかもしれません。
このように、Webサイトのコンセプトでは、制作そのものの目的だけでなく、中長期的な視点も必要になります。それにより、必要な技術、体制、予算などが具体的に見えてきます。
コンセプトの具体化
設定されたコンセプトに基づき、Webサイトの制作を進めるには、関係者全員でコンセプトの解釈が異ならないように注意する必要があります。そのため、誤解を生む表現や意味の分かりにくい表現は避け、全員にとって理解しやすく応用が利くものであることを意識します。
しかし、この段階ではまだ各関係者にとってわかりやすいものではないかもしれません。そのため、制作チームごとに目標達成に迎えるよう、チーム別のコンセプトに落とし込むことが一般的です。
システムコンセプトは、システム開発チームが達成すべき目標となります。この目標を達成するためのデータベース設計、サーバー設計、開発設計などの仕様・要件定義を行います。ユーザーがWebサイトに求める水準はどんどん上がっており、ただ機能を実現するだけでは不十分です。そのため、読み込み速度や将来的な拡張性なども考慮した目標を設定しましょう。
デザインコンセプトは、共同サイトの差別化の方法やオリジナリティのアピール、ターゲットへの訴求力が重視されます。ただキレイなだけのデザインに価値はありません。ユーザーにとって使いやすく、Webサイトの目的を達成するために適切な導線が用意されたデザインを考案する必要があります。
マーケティングコンセプトも、Webサイトの目的を達成するために必要な広告手法や予算、SEO対策などを企画するための指標になります。
まとめ:Webサイトにはコンセプトメイキングが欠かせない
今回は、Webサイトを制作やリニューアル、運用において欠かせないコンセプトメイキングをテーマにお送りしました。
Webサイトを活用する企業が増え始めたとき、「とりあえずWebサイトを作っておくか」というコンセプトのないWebサイトも多くありました。しかし、Webサイトを公開するということは、全世界からそのWebサイトにアクセスされる可能性があるということであり、多くのユーザーはそのWebサイトにある情報のみでその企業やサービスを判断します。
そのため、コンセプトのないWebサイトはブランディングに悪影響を与えたり、ビジネスチャンスを喪失したりする可能性があります。誰もがインターネットを通じて情報を得ている現代だからこそ、「とりあえず作っておくか」というWebサイトは通用しなくなっています。
今回紹介したものは、コンセプトメイキングに必要な最低限の要素です。実際には、企業の体制や目的、業種や現状によって、求められるコンセプトメイキングの手法も変わってくるでしょう。さらに、設定したコンセプトをサイトデザインにどう落とし込むかも、企業のイメージに欠かせません。これからWebデザイナーになろうとしている方は、どうやってコンセプトをサイトに落とし込むのか学んでおくとよいでしょう。