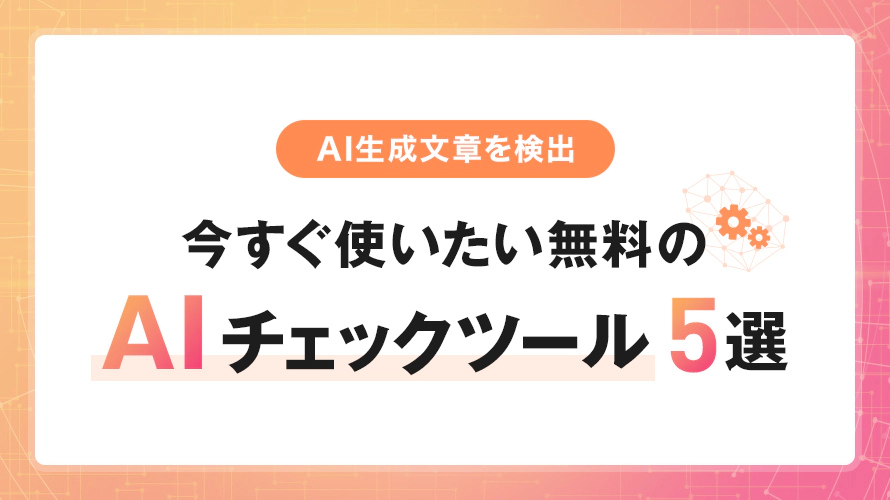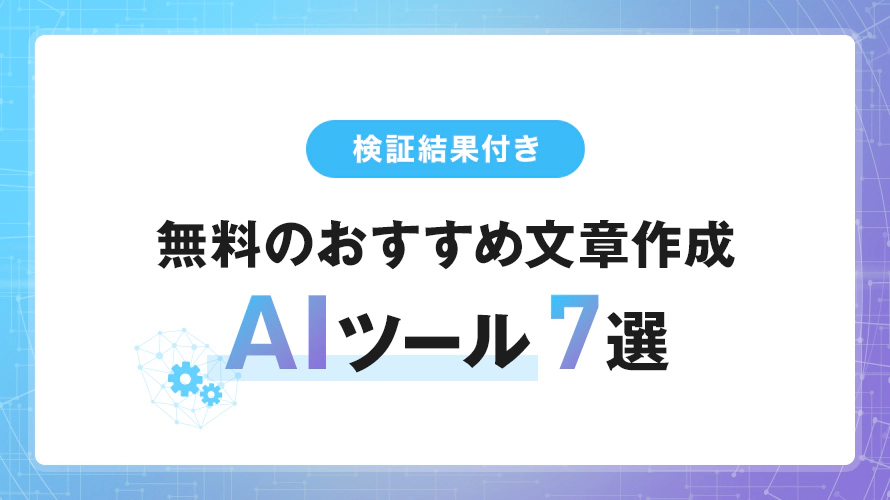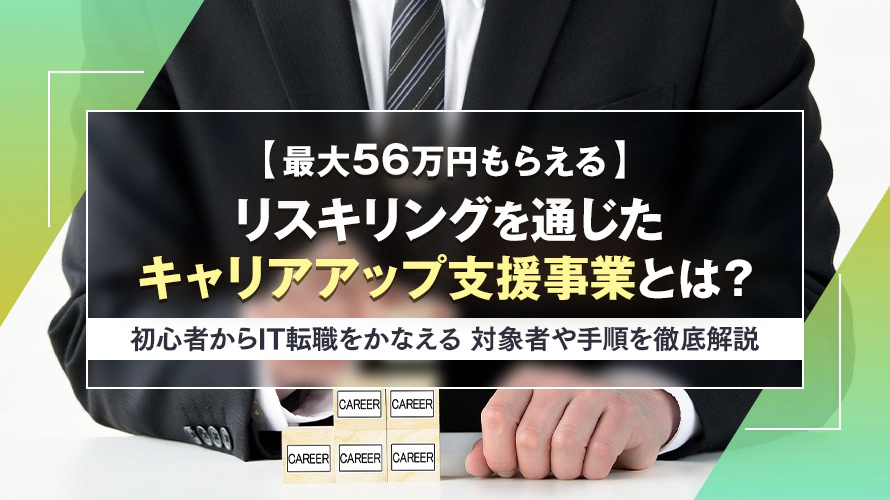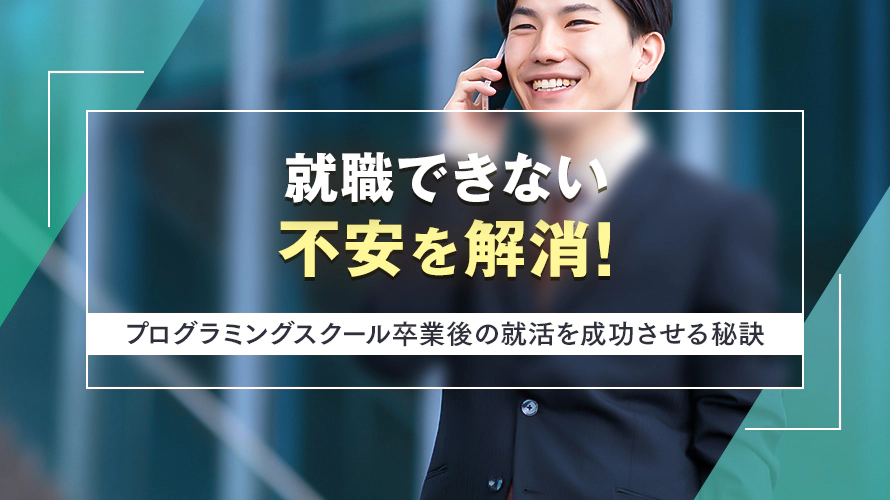生成AIが引き起こすハルシネーションとは?嘘を防ぐための対策プロントを紹介
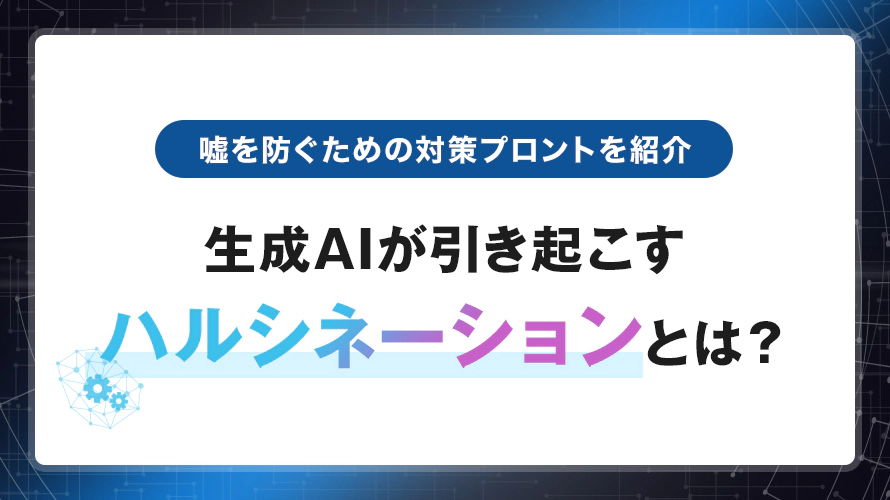
「生成AIのハルシネーションとはどういった現象なのか?」
「どのようにすればハルシネーションを防ぎ、正確な情報を得ることができるのか?」
生成AIの普及に伴い、このような疑問や不安を抱く方も増えています。ハルシネーションは、生成AIが本来持つべき情報の信頼性を損なう原因の一つであり、適切な対策が求められます。
本記事では、生成AIにおけるハルシネーションの概要、発生する原因や影響、さらにそれを防ぐための具体的な方法について解説いたします。生成AIの利便性を最大限に引き出し、信頼性のある活用を目指すために必要な知識をお伝えします。生成AIの利用において留意すべきポイントをしっかりと理解し、安全かつ効果的に活用できるよう、ぜひ最後までご覧ください。
ハルシネーションとは?その基本の理解

生成AIの分野で「ハルシネーション」とは、AIが現実とは異なる、あるいは事実でない情報を出力してしまう現象を指します。もともとハルシネーション(Hallucination)とは「幻覚」や「幻影」を意味する言葉で、生成AIが実際には存在しない情報をあたかも真実のように提示してしまうことから、この名称が使われるようになりました。
生成AIが出力するテキストは、過去のデータに基づいて予測された内容ですが、必ずしも真実とは限らない場合があります。このため、生成AIが提示する情報をそのまま信頼することにはリスクが伴います。特に、ビジネスや教育、医療など、正確性が求められる場面での利用においては、こうしたハルシネーションを見極め、制御する手段が重要となります。
ハルシネーションの事例
今回はChatGPT 4.0 miniを使用し、ハルシネーションが発生しやすい質問を意図的に投げかけ、ハルシネーションを発生させた事例を2つご紹介します。ぜひ参考にしてください。さらに、「女性の投票率の上昇の要因が投票啓発活動や社会的な意識変化」と回答していますが、その因果関係も不明確で、あたかも事実であるかのような表現を用いているだけのように思われます。
なお、日本政府観光局(JNTO)発表統計をもとにしたJTB総合研究所の2023年地域別訪日外国人数データでは、中国が9.7%、韓国が27%、アメリカが8.2%、欧州諸国が6.6%と示されています。大阪・関西万博の海外来場者の国別割合と訪日外国人の国別割合が一致するとは限りませんが、訪日外国人の国別割合と比較すると、ChatGPTの回答には大きな乖離があることがわかります。
ハルシネーションの原因
生成AIがハルシネーションを引き起こす原因は、複数の要因が重なることで発生します。この現象を理解するには、生成AIの構造や学習プロセスの特性を把握することが重要です。以下では、主な原因をいくつか紹介します。
学習データの偏りと影響
生成AIは膨大なテキストデータをもとに学習していますが、データの選定や偏りによって誤った情報を生成する場合があります。例えば、特定の分野や視点に偏ったデータが含まれていると、その内容に沿ったハルシネーションが発生しやすくなります。また、古いデータや誤情報が学習に含まれている場合も、AIの回答に誤りが含まれるリスクが高まります。モデルの限界と構造的な要因
生成AIは学習データをもとにパターンを認識し、統計的な予測を行う構造です。そのため、真実や現実といった概念を理解しているわけではなく、あくまで「もっともらしい」回答を生成する仕組みです。この構造的な限界が、事実と異なる回答や根拠のない情報を出力する原因となります。特に複雑な質問や具体的な事例については、学習データに含まれない内容を想像で補完するため、ハルシネーションが発生しやすくなります。入力プロンプトによる影響
ユーザーが入力したプロンプトの内容も、ハルシネーションの発生に影響を与える要因の一つです。質問があいまいであったり、詳細が不足している場合、生成AIは関連性の高い情報を補完しようとし、結果的に事実とは異なる情報を出力することがあります。また、プロンプトが誤解を招く内容であったり、誤情報に基づく場合、生成AIもその誤りに引きずられた回答を生成する可能性が高まります。ハルシネーションを理解し、最小限に抑えるためには、これらの原因に基づく対策が不可欠です。次のセクションでは、ハルシネーションを防ぐための具体的な方法について解説します。
【プロンプト例を紹介】ハルシネーションの防止・対策

生成AIが誤った情報を提供してしまう「ハルシネーション」は完全に防ぐのは難しいですが、いくつかの工夫でリスクを減らすことができます。ここでは、ハルシネーションを防ぐために役立つシンプルな対策方法を紹介します。
信頼できる情報源を指定する
プロンプト例
データの更新日を指定する
プロンプト例
プロンプトに根拠を求める記述を加える
「回答に含まれる情報の根拠を具体的に示してください」と指示することで、AIがその回答をどうして出力したかを明らかにしやすくなり、信頼性を確かめることができます。プロンプト例
不明確な場合は回答を控える指示の活用
プロンプト例
ハルシネーションの特徴・見分け方
生成AIが出力した情報が正しいかどうかを見極めるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、ハルシネーションの特徴と見分けるための基本的なチェック方法を紹介します。
矛盾点を探す
まず、生成AIが提供した情報が一貫性を保っているか、また論理的に矛盾がないかを確認しましょう。同じ文脈内で異なる情報を示している場合や、話の流れが不自然に感じる場合は、ハルシネーションの可能性があります。例えば、生成AIが「日本の首都は東京です」と答えた後に「日本の首都は京都です」と述べている場合、一貫性がなく、ハルシネーションの可能性があります。このように矛盾がないかを確認することで、誤情報を見つけやすくなります。
あいまいな表現を探す
「おそらく」「一般的に」「よく知られている」といった曖昧な表現が多い場合、信頼性が低いことが多いです。例えば、以下のような表現が含まれている場合、曖昧な表現が多いため注意が必要です。- 「おそらく、この技術は将来の主流になるでしょう。」
- 「一般的に、この方法が成功することが多いとされています。」
- 「よく知られているように、AIは様々な分野で活用されています。」
- 「おそらく、多くの人がこの結果に驚くかもしれません。」
- 「一部では、この製品が最も効果的であると言われています。」
現実離れした内容
明らかに現実と異なる情報や、信じがたい内容が出てくる場合もハルシネーションの特徴です。例えば、「AIがすべての病気を治すことができる」「人類が月に村を作った」など、突飛な内容は事実ではない可能性が高いです。信頼できる情報源との比較(ファクトチェック)
ハルシネーションの疑いがあるときは他の信頼できる情報源でファクトチェックすることも大切です。インターネットで調べたり、専門家の意見を確認したりすることで、AIの出力内容が正確かどうかを判断できます。特に専門的な知識が必要な内容については、必ず他の情報源と照らし合わせ、ファクトチェックを行うようにしましょう。生成AIにおけるハルシネーション以外の注意点

生成AIの利用においては、ハルシネーション以外にも注意すべきポイントがあります。以下に挙げるのは、生成AIを安全に使いこなすために押さえておきたいその他のリスクです。
プライバシーとセキュリティのリスク
生成AIを利用する際には、プライバシーやセキュリティの問題にも気を付ける必要があります。特に個人情報や機密情報を扱う場面では、誤って情報が外部に漏れるリスクがあります。AIを活用する際は、取り扱うデータの管理に十分注意しましょう。偏見や差別の回避
生成AIは学習データに基づいて出力を行うため、学習データに偏りがあると、それがAIの回答にも反映されてしまいます。その結果、不適切な内容や偏見が含まれた出力が生成されることがあります。AIを利用する際は、出力内容が公平であるかを確認し、偏見や差別を避ける工夫が必要です。知的財産権の問題
生成AIが出力した情報には、著作権や知的財産権の問題が関わる場合もあります。特に、AIが生成したコンテンツをそのまま使用する場合、元データに由来する情報が含まれている可能性があるため、注意が必要です。生成コンテンツを利用する際には、知的財産権についても十分確認し、必要に応じて権利関係をクリアにすることが大切です。著作権や知的財産権の防止にはAIチェックツールを活用できます。詳細については以下の記事を参考ください。
ハルシネーションに関する質問

生成AIのハルシネーションについて、ユーザーからよく寄せられる質問をいくつかご紹介します。ハルシネーションの理解を深め、安全にAIを活用するためのヒントにお役立てください。
Q1. 生成AIがハルシネーションを起こさないようにすることは可能ですか?
Q2. 生成AIが出力した情報がハルシネーションかどうかをすぐに見分ける方法はありますか?
A. 簡単な方法として、他の信頼できる情報源と比較したり、一貫性や論理性を確認したりすることで見分けることができます。Q3. ハルシネーションが発生しやすい質問や条件はありますか?
A. 一般的に、曖昧な質問や具体的なデータを伴う質問ではハルシネーションが起こりやすい傾向があります。質問を明確にし、詳細を付け加えることでリスクを抑えられる場合があります。まとめ
生成AIのハルシネーションは、誤情報を出力するリスクがあるため、AIの活用において注意が必要です。本記事では、ハルシネーションの概要や原因、そしてその防止・対策方法について詳しく解説しました。AIの出力内容を信頼できる情報源で確認したり、一貫性や具体性をチェックしたりすることで、ハルシネーションのリスクを抑え、安全にAIを利用することができます。生成AIを効果的に活用するために、ぜひこれらのポイントを活用してください。
生成AIのハルシネーションやその対策を理解することで、AIをより効果的に活用できます。しかし、AIツールに頼るだけでなく、AIライティングのスキルを身につけることで、さらに高品質な文章を作成することが可能です。これからますます需要が高まるITスキルを学ぶには、専門的なスクールでの学習も有効な手段です。
マナビタイムでは、AIライティングを学べるスクールを多数掲載しています。また、5分ほどであなたのITスキルを見える化し、IT業界での市場価値が明らかになるITスキル診断ツール『ミライマップ』も運営中。気になった方はぜひお試しください。