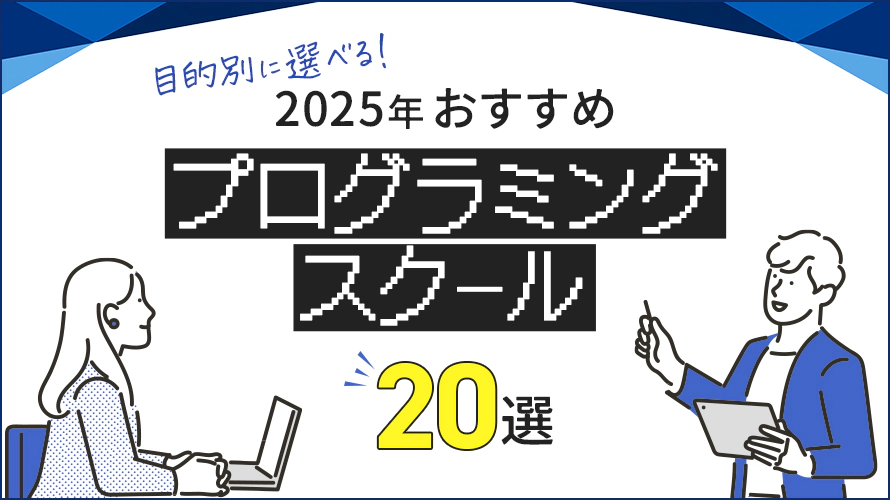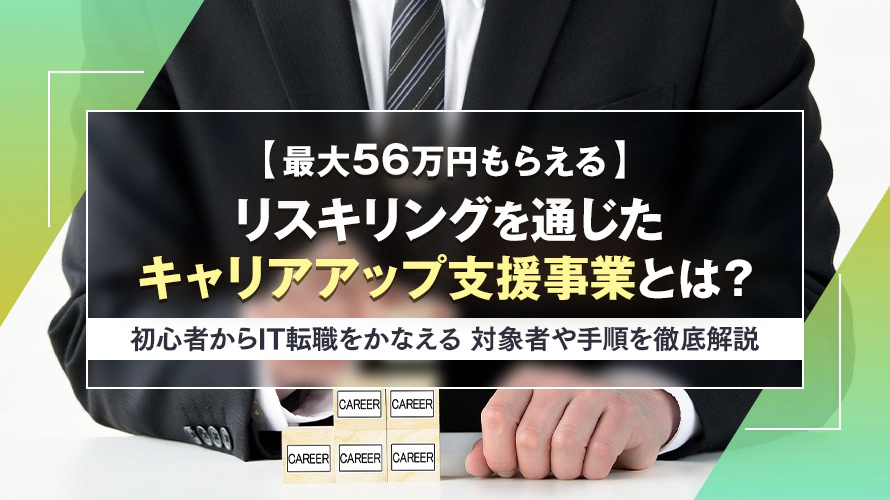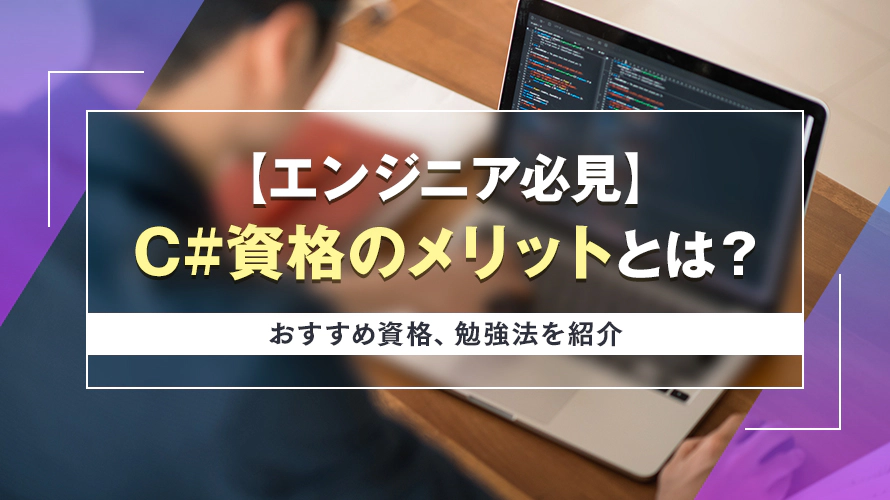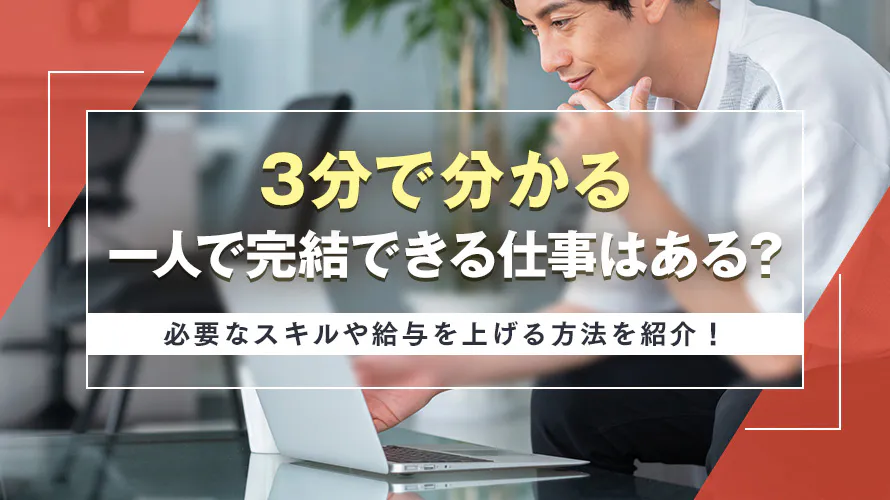Linuxの資格取得がおすすめな理由とは?主要資格と勉強方法も解説
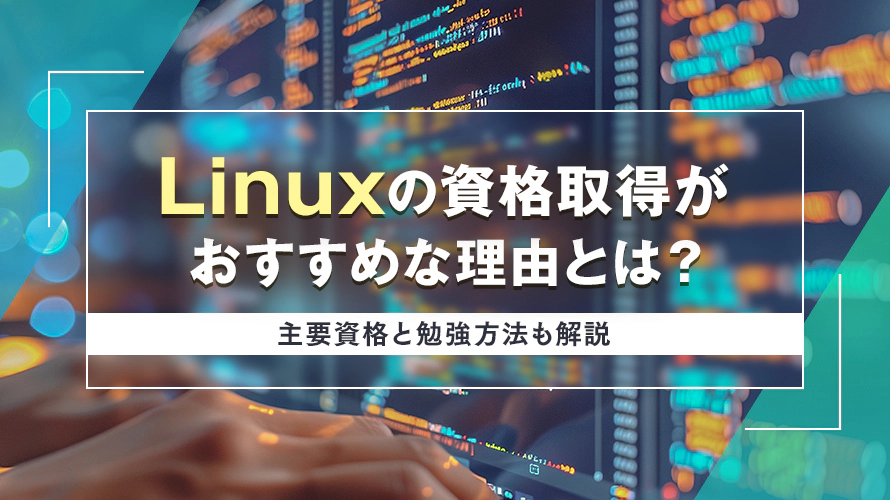
Linux(リナックス)は、オープンソースソフトウェア(OSS)の代表格といわれ、サーバーOSとして人気を集めています。Linuxに関連する資格はIT業界でも需要が高いため、取得を目指している方は多いでしょう。
この記事では、Linuxに関連したおすすめの資格やその特徴、難易度を紹介。
Linuxの資格を取得するメリット、目指せるキャリア、資格取得に向けた勉強方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
- Linuxの主要資格4種(LPIC・LinuC・RHCSA・LF認定資格)の特徴と違い
- Linux資格のメリットやキャリアアップにつながる可能性
Linuxのおすすめの資格4種
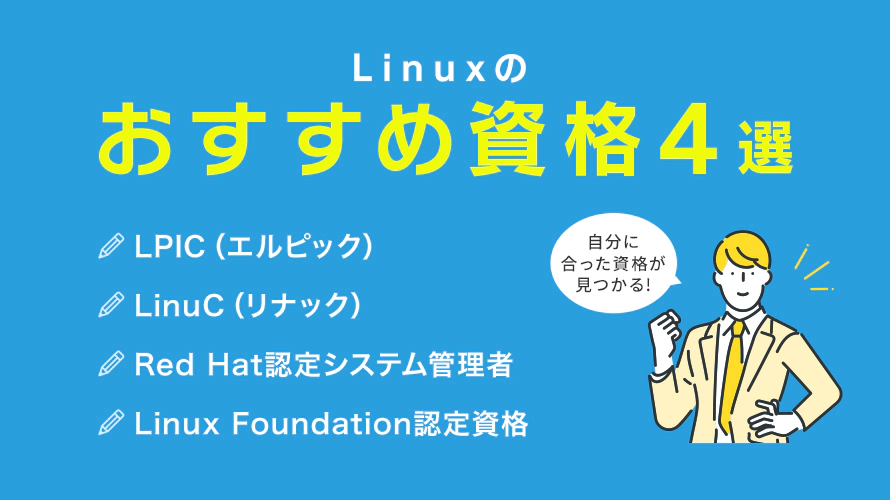
さっそく、Linux関連でおすすめな資格を紹介します。世界標準として代表的な資格から初心者向けの資格なども紹介しているので、自分に合った資格選びに役立ててください。
世界標準の「LPIC(エルピック)」
LPIC(エルピック)は、「LPI認定資格」「Linuxプロフェッショナル認定資格」とも呼ばれており、世界中で実施されているLinux技術者認定試験です。正式名称は「Linux Professional Institute Certification」で、国際的に通用する資格です。
レベル1からレベル3まで、3つのグレードに分類されています。中でもLPIC-1はLinuxを使ったサーバー構築に関する基礎知識を身に付けられるため、初心者にもおすすめな資格です。
なお、2018年にNPO法人 LPI JAPANが新たにLinuCという資格を運営し、LPICの運営を終了したことから、LPICの廃止が噂されたこともあります。しかしその4カ月後に設立されたLPI 日本支部がLPICの経営を発表し、LPICの廃止はただの噂だったことが証明されています。
LPIC(エルピック)取得可能なコースが学べるITスクールのコース一覧
日本独自の「LinuC(リナック)」
LinuC(リナック)の正式名称は「Linux技術者認定試験 LinuC(リナック)」です。日本独自のLinux試験として、2018年度からLPI JAPANが実施しています。
オンライン受験もできるため、試験会場まで足を運ばなくても受験可能です。
資格試験はレベル1からレベル3までの3つに、システムアーキテクトを加えた4つのレベル別となっています。レベル1はLinuCの資格の中でも1番難易度が低い試験であるため、初心者にもおすすめです。
LinuC(Linux技術者認定資格リナック)取得可能なコースが学べるITスクールのコース一覧
Red Hat 認定システム管理者(RHCSA)
Red Hat認定システム管理者(RHCSA)は、世界中で実施されているLinux認定資格です。レッドハット社が主催しており、RHCSA認定試験(EX200)に合格すると認定が付与される資格です。試験は全て実技でさまざまなツールを使用したり、スクリプトを作成したりして、実際の開発タスクを行います。そのため試験合格に向けて、勉強することで実践的な技術を得ることができます。
基本的な知識やスキルが問われる試験なので、経験が浅い人でも十分に勉強をして挑めば合格可能な試験です。
Linux Foundation認定資格
Linux Foundation認定資格は、非営利団体のLinux Foundationが提供している国際的な認定資格です。
Linux Foundation認定資格にはさまざまな種類があり、資格によって試験内容が異なります。試験は実技で行われるため、現場で生かせる実用的なスキルを身に付けられます。
Linux以外の知識や技術も求められるため、LPICやLinuCと比べても難易度が高いです。
Linuxの関連資格を取るメリット

ここでは、Linuxに関連する資格取得を目指すことによるメリットをいくつか紹介します。
Linuxの専門知識が身に付く
資格取得のための勉強を通して、Linuxに関する専門的な知識を幅広く学習できるメリットがあります。
資格の種類はレベル別に分けられているケースが多いため、自分の知識レベルに合った専門知識を身に付けられます。
世界に通用する重要度の高いスキルが身に付く
LPICやRed Hat認定システム管理者など、世界共通の資格を取得することで国際的に重要度の高いスキルを身に付けられます。外資系や海外への転職活動にも役立つでしょう。
Linux以外の知識を求める問題が出題される場合もあり、セキュリティや仮想化技術、サーバー構築などの幅広い知識や実践的な技術を身に付けることも可能です。
選択肢が広がり、キャリアアップに生かせる
Linux関連の資格を取得すれば、専門的な知識やスキルを有している証明となるため、IT技術者としてアピールが可能になります。
LinuxはサーバーOSやアプリケーションの動作環境など、さまざまな分野で活用できるため、仕事の幅が広がり、キャリアアップにもつなげられるでしょう。
Linux関連資格の試験内容や難易度
Linuxに関連する資格の試験内容や難易度について、「LPIC」「LinuC」を例に用いて解説します。
LPIC:試験内容と難易度
LPICはLPIC-1からLPIC-3へと難易度が上がっています。それぞれのレベル別の試験内容と難易度は以下の通りです。
| レベル | LPIC-1 | LPIC-2 | LPIC-3 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 90分 | 90分 | 90分 |
| 出題数 | 60問 | 60問 | 60問 |
| 出題形式 | 多肢選択式 記述式 | 多肢選択式 記述式 | 多肢選択式 記述式 |
| 出題範囲 | 101試験 102試験 | 201試験 202試験 | 300試験 303試験 305試験 306試験 |
| 合格ライン | 非公開 (65~75%程度とされる) | 非公開 (65~75%程度とされる) | 非公開 (65~75%程度とされる) |
| 難易度 | 最低限の基礎知識が必要 | プロフェッショナルとしての基礎知識が必要 | プロフェッショナルとしての応用知識が必要 |
LPC-1やLPIC-2は2つの試験を受ける必要があり、どちらかが合格して5年以内にもう1つの試験も合格しなければ無効となります。LPIC-1であれば、101試験に合格後、5年以内に102試験に合格しなければいけません。
LinuC:試験内容と難易度
LinuCはレベル1からレベル3、システムアーキテクトへと難易度が上がっています。それぞれのレベル別の試験内容と難易度は以下の通りです。
| レベル | 試験時間 | 出題数 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 90分 | 約60問 | 基本操作とシステム管理に関する知識が必要 |
| レベル2 | 90分 | 約60問 | 仮想環境を含むLinuxのシステム設計などにおいて、アーキテクチャに基づいた設計・導入・保守・問題解決ができる知識が必要 |
| レベル3 | 90分 | 約60問 | 最高技術レベルのLinuxプロフェッショナルの知識が必要 |
| システムアーキテクト | 90分 | 約40問 | プレイングシステムアーキテクトとしての知識とスキルが必要 |
出題形式はLPIC同様、多肢選択式・記述式、難易度も65~75%程度とされており、LPICと類似しています。また、レベル1やレベル2、システムアーキテクトは2つの試験を受けなければならず、1つを合格した日から5年以内にもう1つの試験も合格しなければ合格は無効となるため、注意が必要です。
Linuxの資格を取得するために必要な勉強時間
Linuxを取得するために必要となる勉強時間の目安を、代表的な資格である、LPICとLinuCを例に解説します。
LPICの学習時間の目安
LPICに合格するためには、以下の学習時間が必要だとされています。
- LIPC-1:1~3カ月程度
- LIPC-2:3カ月~半年程度
- LIPC-3:半年~1年程度
知識量や経験の有無でも勉強時間は変動する上、1日で確保できる勉強時間によっても期間は異なります。
いずれも独学の場合の目安であるため、ITスクールに通うことで効率的な学習が可能となり時間を短縮できるでしょう。短期間で取得したい場合は、ITスクールの利用を検討するのがおすすめです。
LPIC(エルピック)取得可能なコースが学べるITスクールのコース一覧
LinuCの学習時間の目安
LinuCに合格するには、以下の学習時間が必要だといわれています。
- LinuCレベル1:1ヵ月~3ヵ月程度
- LinuCレベル2:3ヵ月~半年程度
- LinuCレベル3/LinuCシステムアーキテクト:半年~1年程度
知識が浅い人を想定した目安期間なので、すでに知識が豊富な人であればより短い期間で習得できるでしょう。
また、独学を想定した学習時間であるため、スクールで学ぶことで時間を短縮できる可能性があります。学習方法や知識量に合わせて、余裕を持った学習スケジュールを立てるのがおすすめです。
LinuC(Linux技術者認定資格リナック)取得可能なコースが学べるITスクールのコース一覧
Linuxの資格を取得するためにおすすめな勉強方法

Linuxの資格取得を目指す際におすすめの勉強方法を解説します。
独学で学ぶ
独学はいつでも気軽にスタートできる方法です。オンライン教材や書籍、問題集を活用して勉強を進めるのが一般的です。さまざまなタイプの教材があるため、自分のレベルや好みに合った教材を選んで勉強できます。
ただし、自分のペースで進められる反面、疑問点が出てきたときは自分で解決しなければなりません。モチベーションを維持し、自分だけで問題を解決できる人に向いている勉強方法だといえるでしょう。
プログラミングスクールで学ぶ
プログラミングスクールに通うことも、有効な勉強方法です。カリキュラムに沿って学習を進められるため、短期間で効率的に知識やスキルを習得できます。また疑問点が出てきた場合も講師に直接聞けるため、すぐに解決できます。
仲間に相談しつつ、モチベーションを維持しながら勉強を進められるのもメリットです。
「プログラミングスクールが近くにない」「金銭的なリスクが不安」という場合はオンラインスクールを検討するのもおすすめです。自分に合ったオンラインスクールをマナビタイムで探してみてください。
Linuxの資格でキャリアアップを目指そう!オンラインで学べる人気のスクールはこちら
Linux関連資格を取得後のキャリアパス
ここからは、Linux関連の資格を取得した後、目指せるキャリアパスをいくつか紹介します。
インフラエンジニア
インフラエンジニアとは、サーバーやネットワークなどの設計・構築・運用・保守を担うエンジニアのことです。サーバーを取り扱う機会が多いため、Linuxに関する知識が欠かせません。
ITインフラを支えるインフラエンジニアは、どの業界にとっても欠かせない存在であり、需要が高い職種です。
セキュリティエンジニア
セキュリティエンジニアは、外部からの攻撃やリスクからネットワークやシステムを守るITエンジニアです。サーバーの構築や運用、保守などを担うのが主な業務内容です。
Linuxはもちろん、セキュリティに関する基礎知識が欠かせず、常に最新の技術を身に付けなければいけません。資格取得に向けて体系的に学ぶことで、業務にそのまま活かせるでしょう。
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアは、クラウド環境を利用したシステムの構築や保守、運用を担当するITエンジニアのことです。
ITインフラをAWSやAzureなどで構築するために、サーバーやネットワークの基礎知識やクラウドに関する深い知識が必要とされます。
クラウドサービスを活用した事業が増えることで、需要が高まる業種だと予想されています。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアとは、ネットワークの設計や構築、保守、運用を担当するITエンジニアを指します。
ネットワークエンジニアを目指すのであれば、業務を効率化するツールとしてLinuxを活用しなければいけません。トラブルシューティングやメンテナンスなど、幅広い業務で実践できます。
サーバーエンジニア
サーバーエンジニアは、ゼロからサーバーを構築・設計し、管理・保守を遂行することが主な業務のITエンジニアです。
Linux関連の資格取得は必須ではありません。しかし多くの企業でLinuxが導入されている上、インターネットサーバーのシェアも大きいため、取得しておくことで転職や就職で有利に働く場合があります。
まとめ:ITスクールで効率よくLinux資格の取得を目指そう
Linux関連の資格は、世界共通の資格として通用するためエンジニアとして活躍したいのであれば取得しておくのがおすすめです。取得を目指す資格のレベルによっては、長期的な学習が必要となります。
効率よくLinux関連の資格取得に向けて勉強をするのなら、ITスクールで学ぶと良いでしょう。近所でプログラミング言語が学べるスクールやコースが見つかる「マナビタイム」を活用して、自分に合ったITスクールを見つけてみてください。
なお、マナビタイムでは、気になるスクールやコースを検討リストに保存し、まとめて問い合わせすることができます。
Linuxやインフラ系の学習を始めたい方は、複数のスクールを比較しながら効率よく情報収集するためにも、まとめて問い合わせを活用するのがおすすめです。気になるスクールやコースの詳細画面から、検討リストに保存して問い合わせてみましょう。
Linuxやインフラ系の学習を始めたい方向けに、おすすめのプログラミングスクールを徹底比較したまとめ記事をご用意しています。